第3章 予算要求
目次
第3章 予算要求
|
PJMOは、情報システム関係予算について本予算及び補正予算における予算要求を行う際には (1)、プロジェクトを立ち上げた上で、次の事項を実施するものとする。 |
プロジェクトを円滑に進めて目標を達成するためには、プロジェクトの活動に必要となる経費を、適切な時期に過不足なく確保することが必要である。その上で、これらの経費の予算要求に当たっては、十分な積算根拠に基づいて客観的に妥当性が判断できるように要求額を算出するとともに、その費用対効果を明確に説明することが不可欠である。
本章は、情報システム関係予算の要求に係る一連の活動の中で遵守、注意すべき事項を示すことで、PJMOがプロジェクトの内容に応じた必要十分な予算を適切に要求できるようにすることを目的としている。
2. 解説(1)「情報システム関係予算について本予算及び補正予算における予算要求を行う際には」
「情報システム関係予算」とは、別紙2「情報システムの経費区分」に示される経費に関する予算をいう。(参考:標準ガイドライン 別紙2「情報システムの経費区分)
「予算要求を行う際には」とは、当該年度の予算要求に係る費用の積算、資料の作成、要求の提出までの範囲だけでなく、資料作成前に行う予算要求の計画及び調整から、予算額の確定までを含んだ期間を指す。
1. 予算要求の対象の特定
|
PJMOは、 予算要求に先立ち、プロジェクト計画書及びプロジェクト管理要領を確認し、プロジェクトの内容や進め方等を踏まえ、情報システム関係予算の要求対象を特定する (1) ものとする。また、PJMOは、予算要求の内容について漏れがなく、かつ、重複がないよう、PJMO内の各担当と確認及び調整を行う (2)ものとする。 なお、単年度の契約を行う場合と比較して、複数年度にわたる契約を行うことに合理性が認められる場合には、国庫債務負担行為の活用を検討する (3)ものとする。 |
プロジェクトは一様ではなく、その特性、規模、実現方法等は様々である。これらの特性等を十分に理解せずに予算要求を行うと、予算額が足りずにプロジェクト運営に支障をきたすことや、逆に予算額が過剰となり必要とされる以上の機能やサービスを調達する等の過大投資や適正な価格での調達がなされず、合理的な調達がなされないなど、事業の効果的・効率的な執行を図る観点から問題となることにつながりかねない。
このため、予算要求に向けた準備活動の中では、予算要求の対象として「どういった目的・目標で、いつ、どの経費を、どの範囲で」要求するかを明確にし、関係する各担当と十分に調整することが重要である。
2. 解説(1)「予算要求に先立ち、プロジェクト計画書及びプロジェクト管理要領を確認し、プロジェクトの内容や進め方等を踏まえ、情報システム関係予算の要求対象を特定する」
「予算要求に先立ち」とは、予算要求に関する活動を開始するときを指す。開始時期は、PMOが定める予算要求のスケジュールや、それに先立つ資料の準備、ベンダーからの見積り取得等に要する期間を踏まえて、決定する必要がある。特に新規に開始するプロジェクトにおいては、事業の目的や目標を踏まえた、プロジェクト計画、サービス・業務企画の方向性、システム化の範囲や概要等、多くの内容を検討する必要があるため、予算要求の前年度又は前々年度から検討に着手する等、十分な事前検討を行う期間と体制を確保するように留意する。
「情報システム関係予算の要求対象を特定する」とは、プロジェクトの目標を達成するために必要な組織、機能、資材などのプロジェクトの全体像(ビジネスモデル)を把握した上で、情報システムが担う部分を特定し、これらを実現するために必要な情報システム関係の調達内容や調達時期を整理する。これにより、調達の全体像を把握するとともに、当該年度の予算要求で要求する調達対象を特定することをいう。特に、複数年にわたり調達が必要となる情報システム関係予算について可視化することで、後年度に必要となる予算要求を把握する。
情報システム関係の調達に必要となる経費と予算要求対象の関係について、その例を図3-1に示す。
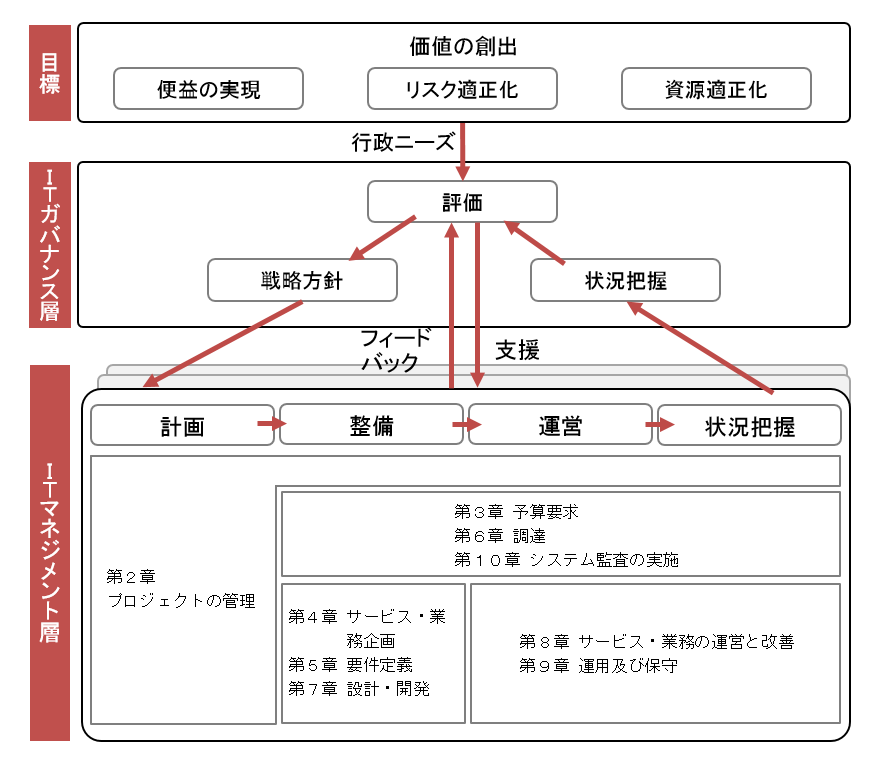
図3-1 予算要求の対象範囲の例
[1] N-2年度に「計画策定支援委託」を実施する。この委託業務に必要となる経費に対して、N-3年度に予算要求を行う。
[2] N-1年度からN年度の2年度にわたり、「設計・開発委託」を実施する。この委託業務に必要となる経費に対して、N-2年度に国庫債務負担行為を活用し2年度分の予算を確保した上で、各年度で予算要求を行う。
[3] N年度からN+4年度の4年度にわたり、「ハードウェア・ソフトウェア等の賃貸借・保守」、「アプリケーション保守委託」及び「運用支援委託」を実施する。これらの業務に必要となる経費に対して、N年度に国庫債務負担行為を活用し4年度分の予算を確保した上で、各年度で予算要求を行う。
(2)「予算要求の内容について漏れがなく、かつ、重複がないよう、PJMO内の各担当と確認及び調整を行う」
「漏れがなく、かつ、重複がない」とは、プロジェクトの活動を行うために必要となる各経費について、他の経費項目や他の担当の予算要求項目との二重計上がなく、必要な項目の計上漏れもない状態を指す。
PJMO各担当は、要求する経費項目にこのような過不足が発生しないように、特に複数の部門で個別に予算要求する場合は、計上項目の分担を行った上で相互に要求内容を確認することが重要である。また、経費項目の計上漏れを防ぐためには、
プロジェクト計画書の実施計画及び別紙2「情報システムの経費区分」と調達単位で突合しながら、調達単位で確認していくことが効果的である。さらに、一つの調達に含まれる経費項目だけではなく、同一プロジェクト内で調達が複数に分かれることも考慮し確認を行う。
なお、複数プロジェクトが関連する場合や情報システム関係予算以外の予算(事業費等)と関係がある場合も、関係者間で同様に確認を行う。
(3)「複数年度にわたる契約を行うことに合理性が認められる場合には、国庫債務負担行為の活用を検討する」
「複数年度にわたる契約を行うことに合理性が認められる場合」とは、事業者の見積り等の根拠に基づき、複数年度の契約が単年度の契約と比較して予算の節減又は執行の効率化につながると客観的に判断できる場合のことを指す。合理性が認められる例を次に示す。
・ 情報システムの設計・開発業務等において、作業が複数年度にわたることが見込まれ、複数年度分を一括して契約することで、年度ごとに契約を分割するよりもコストが抑制できるもの。
・ 情報システムの保守・運用業務等において、恒常的に必要となる業務であり、過去の実績等から必要となる業務量を十分に予測することができ、複数年度分を一括して契約することで予算の効率的な執行につながるもの。
・ ハードウェア等の購入において、リース契約を用いて複数年度にわたる契約を行うことで、各年度の予算額の平準化に寄与するもの。
・ クラウドサービス等、業務量の変化に応じてリソース量を柔軟に調整するために、サービスの基本部分とリソース利用部分を分けて契約する等したもの。(なお、リソース利用部分の契約は単価契約とする。)
・ 複数年の契約をすることで、長期契約割引等が適用され、業務変動を考慮した単年度契約を繰り返すよりもなおコストメリットが得られるもの。
なお、上記に該当する場合を除き、業務量の変動可能性が大きく業務量を予測することが難しい業務でコストメリットがない一括契約や、複数年に工程を分割しての開発で、後工程の内容や規模が前工程の結果をうけて変化するものについては、原則、合理性が認められるとはいえない。
2. 資料の準備
|
PJMOは、情報システム関係予算の要求に当たって、PMOが定めるスケジュール及び提出を求める資料を確認し、要求内容及び費用対効果の合理性が十分に判断できる資料となるよう、計画的にこれを準備する (1)ものとする。また、 事業者から見積りを取得する際は、事業者から有用な見積りを得られるよう、見積り対象工程に応じた適切な資料を準備する (2) ことに留意する。 なお、内閣官房又は総務省からの資料提供の求めに際して必要となる資料は、例えば次のようなものがある。 <提供を求める資料例 (3)> [1] 予算要求の概要 [2] 予算要求明細書(目細レベルの要求額、その積算内訳(数量、工数、単価等)、事業者の見積書、前年度予算額との対比) [3] プロジェクト計画書 [4] サービス・業務の説明資料(サービス・業務内容、サービスモデルの概念図、業務フロー、業務量実績等) [5] 情報システムの説明資料(役割、対象範囲、主要利用者、主要機能、システム全体構成等) [6] 想定する効果、目標指標(KGI、KPI) また、既存の情報システムがある場合は、併せて次のような資料が必要となる。
<既存の情報システムについて提供を求める資料例 (4)> [1] 過去の事業がもたらした効果と、情報システムが果たした役割 [2] 情報システムの運用コスト削減に向けた取組の説明資料 [3] 情報システムの運用実績(アクセス件数、処理件数等) [4] 情報システムの稼働実績(CPU使用率、ディスク使用率、ネットワーク使用率等) [5] 要求事項と同等の内容の直近の調達結果の詳細(契約日、契約額、契約期間、応札者数、契約相手方等) |
プロジェクトの目標を高い費用対効果で実現するためには、実現するサービス・業務の具体像や情報システムの具体的要件について事業者に正確に情報を伝えることで、精度の高い見積りを取得することが不可欠である。また、PJMOがこれらの情報に基づいて作成する予算要求資料は、PMOや会計担当部門等の関係者がその内容と費用対効果を適切に理解・判断できるように、正確かつわかりやすい内容でまとめることが重要である。
予算要求に必要となる資料は、サービス・業務企画(第4章)や要件定義(第5章)の作業を同時並行的に行い、各々の検討内容と連携し、整合をとりながら作成を進めることとなる。現状分析、検討、関係者調整等の作業に長い時間を要することを踏まえて、資料の準備を計画的に行うことが重要である。
2. 解説(1)「要求内容及び費用対効果の合理性が十分に判断できる資料となるよう、計画的にこれを準備する」
「要求内容及び費用対効果の合理性」とは、実現するサービス・業務の内容、効果、投資額等が、仮定や推測ではなく事実や根拠に基づいて示され、プロジェクト目標の達成に対して整合が取れていることをいう。合理性を判断する観点の例を次に示す。
・ 実現するサービス・業務の内容が、社会的な要請に基づいている。
・ 実現するサービス・業務の内容が、社会や利用者の価値最大化に寄与する内容になっている。
・ 想定されるサービス・業務の提供レベルが、施策目的やサービス内容・目標等に鑑み、必要かつ十分であり過大になっていない。
・ 想定する効果が、過去又は類似の運用実績、利用者に対する調査等の事実情報に基づいて算定されている。
・ 現状の業務の課題が、現場のニーズや実態に基づいて抽出されている。
・ 実現しようとしている業務プロセス・機能が、その目的に照らして必要かつ十分であり、現場等の過度な要求を反映しすぎていない。
・ 実現するサービス・業務に対して、情報システムが担うべき役割、期待する効果が明確になっている。
・ 要求額が、正確な情報に基づき見積もられ、詳細に精査されている。
・ 情報システムに要求する機能や性能等が、運用実績や利用実績等の実データに基づいて検討されている。
「計画的にこれを準備する」とは、上述のような観点から合理性を十分に説明できる資料を作成するために、基礎的な事実情報の把握による現状分析、実現するサービス・業務の検討、関係者調整等を十分に行うための期間を確保して、資料の準備作業を計画し、実施することをいう。
なお、現在も情報システムを運用しているプロジェクトについては、情報システムの運用実績、利用実績等を日々の運用活動の中で収集し、予算要求時に活用できる情報を日常的に蓄積しておくことが重要である。
(2)「事業者から見積りを取得する際は、事業者から有用な見積りを得られるよう、見積り対象工程に応じた適切な資料を準備する」
「有用な見積り」とは、見積りの対象範囲が事業者に求めている内容に合致し、見積り対象工程に応じた適切な粒度で、見積りの内訳が機能単位や製品単位等で細分化された単位で積算され、経費の妥当性について客観的な説明が可能なものを指している。
「見積り対象工程に応じた適切な資料」とは、プロジェクトの状況と対象工程に応じて要件の確定度合や資料の記載粒度を適切に調整した資料のことである。
具体的には、業務自体が新規に発生する場合や業務自体は存在しているが情報システムを初めて整備する場合等においては、根拠とできる事実情報が比較的少ない。そのような状況下で、情報システムに求める要件については主たる部分を確定させた上で詳細部分については後続工程で検討することとなるため、比較的記載粒度が大きな資料となる。また、法律や制度改正対応において、制度自体が固まっていない時点で予算要求を行わなければならない局面においても同様に、詳細化を後続工程で実施することとなる。
一方で、既に情報システムを運用しているプロジェクトで、明確な要件に基づいて改修を行う場合等においては、業務における各種情報や情報システムの設計情報、運用情報等の多量の根拠に基づいて、情報システムに求める要件を精緻に定めることができる。
このようにプロジェクトの状況と対象工程に応じて検討の粒度が異なることに留意し、適切な資料を準備することが重要である。
(3)「提供を求める資料例」
「提供を求める資料例」とは、内閣官房及び総務省が「第2編第6章1.2) 要求内容等の把握」の実施に当たって、要求状況を把握するためにPJMOに提出を求める資料の例である。
資料の内容を、表3-1に示す。
表3-1 提供を求める資料例の内容及び作成する資料 |
(4)「既存の情報システムについて提供を求める資料例」
「既存の情報システムについて提供を求める資料例」とは、既存の情報システムがある場合に、(3)に併せて追加で必要となる資料の例である。
資料の内容を、表3-2に示す。
|
3. 経費の見積り
|
PJMOは、予算要求の積算に当たって、次の[1]から[8]までに掲げる事項を遵守するものとする。なお、 補正予算の場合は、予算要求までの期間が短くなるため、予算要求後にも見積りの対象や金額について精査を行う等、進め方に留意する必要がある (1) 。 |
[1] IT基本法第26条第2項第2号の規定に定める経費の見積り方針に従う (2)こと。
[2] 事業者から見積りを取得するときは、実現したい業務・機能の内容、規模、サービスレベル、スケジュール等、事業者が見積りをするための必要な情報の提供を行う (3) こと。
[3]見積り金額の妥当性を確認できるように、数量、工数、作業者のレベル、単価等の積算内訳を明確にする (4)こと。
[4] ライフサイクルコストを見積り、その根拠を明確にする (5)こと。
[5] 情報システム単位で積算し、区分できるようにする (6)こと。
[6] 「別紙2 情報システムの経費区分」に基づき区分する (7)こと。
[7] 原則として複数事業者の見積りを比較する (8)こと。
[8] 原則としてクラウドサービスの利用を前提とした見積りも取得する (9)こと。
1. 趣旨経費の見積りに当たっては、予算額が足りずにプロジェクト運営に支障をきたすことや、逆に予算額が過剰となり事業の効果的・効率的な執行を図る観点から問題となることがないよう、プロジェクトの内容に応じた必要十分な水準とすることが求められる。また、PMOや会計担当部門が費用対効果を正しく判断できるよう、客観的な妥当性を担保することが求められる。
このため、本項で記載した留意点を念頭に置いた上で、十分な期間を確保して計画的に経費の見積りを進めることが重要である。
なお、事業者からの見積りの取得に際し、検討内容に不足がある場合、想定と大きくかい離する見積りが提示された場合、又は、これまで検討されていなかったサービス・業務の実現に係る有用な情報を得られた場合は、「2.資料の準備」に立ち戻って再度検討を行うことが必要である。
2. 解説(1)「補正予算の場合は、予算要求までの期間が短くなるため、予算要求後にも見積りの対象や金額について精査を行う等、進め方に留意する必要がある」
「進め方に留意する」とは、補正予算の予算要求までに十分な精度の根拠に基づいた見積りが行えない場合は、予算執行までの期間にサービス・業務企画や要件定義の詳細化を図り、修正した上で、見積りの対象や金額について精査を行うことを指す。また、補正予算で開始したプロジェクトは、府省重点プロジェクトの対象候補となる。
なお、対象となった場合は、調達仕様書に添付する要件定義書の作成終了前までに第一次工程レビューを実施する等、PJMOはPMOと連携しながら検討活動を行う。
(2)「IT基本法第26条第2項第2号の規定に定める経費の見積り方針に従う」
「経費の見積り方針」とは、IT基本法第26条第2項第2号にて内閣総理大臣が政府CIOに行わせることができる事務の1つとして定められた「関係行政機関の経費の見積りの方針の作成」を指す。予算要求に当たっては、本ガイドラインの要求事項及びPMOが定める方針に加えて、政府CIOが作成する経費の見積りの方針に従う必要がある。
(3)「事業者から見積りを取得するときは、実現したい業務・機能の内容、規模、サービスレベル、スケジュール等、事業者が見積りをするための必要な情報の提供を行う」
「事業者が見積りをするための必要な情報の提供」において、既存の情報システムがあるときには、見積りを依頼する事業者に対し、秘密保持契約を結んだ上で、各種設計書等の閲覧を行わせるよう留意する。
(4)「見積り金額の妥当性を確認できるように、数量、工数、作業者のレベル、単価等の積算内訳を明確にする」
「数量、工数、作業者のレベル、単価等の積算内訳を明確にする」とは、見積りの内訳を「一式 ○○円」といった記載にするのではなく、見積り金額を十分に精査し妥当性を確認できる粒度で内訳を記載することである。
例えば、ハードウェアやソフトウェア等を購入する場合は、購入する物品の品目それぞれに対して、数量、単価を明確にする。ただし、一体として扱える機器等について無理に分割して積算させるようなことはしない。
また、作業を委託する場合は、作業の成果物(開発する情報システムの機能等)それぞれに対して、作業内容、作業工数、作業者種別及びレベル(SE、プログラマ等)、人件費単価を明確にする。作業工数の妥当性を説明できるようにするため、工数算定の根拠を示す基本的数値及び算定方法(画面数、帳票数、LOC、ファンクションポイント等)も併せて記載する。
リース期間が満了となりその後も継続的に情報システムを利用する場合は、再リース契約等による当該物品の継続利用と情報システムの更改とを比較し、どちらがより経済的であるか検討する。
なお、制度変更が予定されているが詳細な変更内容が決定していない等、予算要求時点で情報システムに求める要件を確定できない場合がある。この場合においても、予算要求時点で判明している状況に基づいて必要と見込まれる要件を設定した上で、数量、工数、単価等の積算内訳に加え、見積り上の前提条件や制約条件を明確にした見積りを取得することが重要である。
特に、運用や保守業務における人件費の見積り取得に当たっては、実際の稼働者数と各人と稼働時間がわかるような見積りを取得する必要がある。
(5)「ライフサイクルコストを見積り、その根拠を明確にする」
「ライフサイクルコスト」とは、情報システムのライフサイクル期間(計画・企画、設計・開発から運用・保守を経て廃止するまでの期間。標準ガイドライン解説書「第3編第1章 ITマネジメントの全体像」参照。)に発生する、情報システムに係る全ての経費を指す。
情報システムに係る経費は、導入時だけでなく、運用段階で経常的に発生する。そのため、費用対効果の判断を適切に行うためにも、情報システムのライフサイクル全体を対象とした経費を把握することが重要である。
また、ライフサイクルコストの見積りに漏れがあると、運用段階や、次期システムへの更改を検討する段階等で追加的な経費が発生し、費用対効果を損なってしまう。このようなことを未然に防止するためにも、事業者に見積りの範囲や精度などに係る根拠の明示を求め、必要な経費項目が計上されていることを確認することが重要である。
(6)「情報システム単位で積算し、区分できるようにする」
「情報システム単位で積算し」とは、1つの情報システムIDに対応する情報システム(ある情報システムのサブシステムであって、情報システムIDを取得している場合を含む。)の単位に従って、予算の積算を行うことをいう。
(7)「「別紙2 情報システムの経費区分」に基づき区分する」
「「別紙2 情報システムの経費区分」に基づき区分する」とは、情報システム単位で、かつ、「別紙2 情報システムの経費区分」で示す区分に従い、積算することを指す。
(8)「原則として複数事業者の見積りを比較する」
「原則として」とは、複数事業者からの見積りの取得を行わない合理的な理由がある場合を例外として扱えることを示している。この合理的な理由の例を次に示す。
・ 特定の事業者のみが保有する専門技術や著作権等の制約により、他事業者への見積り依頼が困難な場合
・ 既存の情報システムに対する部分的な改修等、当該情報システムの設計・開発業務や保守業務を行っている既存事業者は設計情報等を熟知しているため作業を効率的に行えるが、その他の事業者は情報システム全体の設計情報等を理解するための先行的な作業に多くの工数を必要とするため、既存事業者と比べて著しく作業規模が異なり、見積りを得ることが困難な場合
・ PMOや府省内外のCIO補佐官、外部組織の有識者や専門的な知見を持つ職員の助言も得ながら可能な限りの事業者へ見積り依頼を行ったが、複数事業者から見積りを得られない場合
事業者に見積りを依頼する際は、同じ粒度で見積りを比較できるように、PJMOが見積り様式を指定し事業者からの提出を求めることが望ましい。また、複数事業者の見積りから要求額を積算する際は、見積り合計額を単純に平均するのではなく、見積りの内訳項目ごとに、見積り対象や前提条件、制約条件等についても精査を行い、内訳項目単位で見積前提の整合がとれた形で比較結果を積算するなど、積算根拠の妥当性を確認することに留意する。
(9)「原則としてクラウドサービスの利用を前提とした見積りも取得する」
「原則としてクラウドサービスの利用を前提とした」とは、IT基本法第26条第2項第3号、「 世界最先端デジタル国家創造宣言・官民データ活用推進基本計画」(平成30年6月15日閣議決定)に基づき、クラウド・バイ・デフォルト原則、すなわち、クラウドサービスの利用を第一候補として検討することを指している。ただし、クラウドサービスの利用が合理的でないときは、例外として扱うことが認められることを示している。
なお、クラウドサービスの導入や事業者からの見積り取得に当たっては、「政府情報システムにおけるクラウドサービスの利用に係る基本方針」を参考に検討する。
4. 府省内での確認
|
PJMOは、PMOの求めに応じて必要な資料を提出し (1) 、要求内容について説明を行うものとする。その際、PMO又は府省CIO補佐官等から指摘、助言又は指導を受けた際は、必要な対応策を講ずるものとする。 |
PMOは、府省内のIT施策に関する全体管理を行うために、各プロジェクトの費用対効果を踏まえた上で予算要求内容の確認を行い、会計担当部門と連携、協力し、予算配分を適正化する役割を担っている。
このため、PJMOは、PMOの定める予算管理の方針に従って、資料の提出を行うとともに、PMO又は府省CIO補佐官等からの指摘、助言又は指導に対しては必要な対応策を講ずる。
2. 解説(1)「PMOの求めに応じて必要な資料を提出し」
「PMOの求めに応じて」とは、PMOが定める予算管理の方針及び手順に従い、予算要求に関する手続を進めることを指す。府省によりPMOのヒアリングの実施等の定めがあるときには、これに係る調整及び対応を手順に基づき実施する。
なお、新規に整備する情報システムの情報システムIDについては、原則として調達時点で取得するものとするが(「第6章2.情報システムIDの取得」参照)、PMOが指示する場合は、予算要求時に情報システムIDを取得するものとする。
「必要な資料」とは、「2.資料の準備」で示す提供を求める資料例を基本として、PMOがPJMOに対して個々に提出を求める資料をいう。
これらには、「2.資料の準備」で示された資料のほか、それらの根拠となる情報(経費の詳細な見積り、効果指標の根拠となる事実情報等)も想定されるため、「2.資料の準備」及び「3.経費の見積り」の事項に従い、予算要求の提出前に資料及び見積りを準備する。
5. 内閣官房及び総務省での確認
|
PJMOは、内閣官房又は総務省の求めに応じて必要な資料(「2.資料の準備」参照)を提出し (1)、内閣官房又は総務省から指摘、助言又は指導を受けた際は、必要な対応策を講ずるものとする。 |
内閣官房及び総務省は、政府全体のITガバナンスを機能させるための諸活動を行う観点から、「第2編第6章1.2) 要求内容等の把握」に基づき予算の要求内容等の調査を行う。これに際し、要求内容等の詳細を把握するため、PJMOに対して資料の提出を求める場合がある。
このため、PJMOは、内閣官房及び総務省からの求めに従い、資料の提出を行うとともに、内閣官房及び総務省からの指摘、助言又は指導に対しては必要な対応策を講ずる。
2. 解説(1)「必要な資料(「2.資料の準備」参照)を提出し」
「必要な資料」とは、「2.資料の準備」で示す提供を求める資料例を基本として、内閣官房及び総務省がPJMOに対して個々に提出を求める資料をいう。
これらには、「2.資料の準備」で示された資料のほか、それらの根拠となる情報(経費の詳細な見積り、効果指標の根拠となる事実情報等)も想定されるため、「2.資料の準備」及び「3.経費の見積り」の事項に従い、予算要求の提出前に資料及び見積りを準備する。
6. プロジェクト計画書の段階的な改定
|
プロジェクト推進責任者は、予算要求の内容について、プロジェクト計画書に反映し、当該計画書の内容を更新する(1)ものとする。また、 必要な情報をODB等へ登録する(2) ものとする。 |
プロジェクト計画書に記載されている予算に係る情報は、プロジェクト全体の予算執行管理や費用対効果の把握のために重要である。
予算要求時に新たに作成した資料についても、プロジェクト計画書の段階的詳細化の一環として、プロジェクト計画書に追加するとともに、調達フェーズにおけるインプット資料として活用するものとする。
予算要求額が確定した際は、速やかにプロジェクト計画書の内容を更新することが重要である。
2. 解説(1)「予算要求の内容について、プロジェクト計画書に反映し、当該計画書の内容を更新する」
「予算要求の内容」とは、主としてプロジェクト計画書の予算(「第2章2.1)オ 予算」参照)を指す。
確定した予算要求額をプロジェクト計画書に反映するとともに、予算査定過程でプロジェクトの実施範囲やスケジュール等に変更が発生した場合は、当該項目の内容も更新する。
(2)「必要な情報をODB等へ登録する」
「必要な情報」とは、予算要求においては、予算要求内容の情報を指す。
ODB登録については「ODB操作マニュアル」を参照すること。